知的なおもちゃ箱。音楽自体も面白いし、作品解釈に関する指標としても引用可能である。エピソードも興味をそそられるものばかり。以下にそのいくつかを記す。
子ども〜学生時代
・子どもの頃はピアノの先生にショパンやワーグナーを禁じらられていて、めちゃくちゃ興味あったので自分でピアノの楽譜を調べて入手していた。50年後にニューヨークでワーグナーを痛烈にディスることになるとは知る由もない。
・オペラが出発点になり、その後有名なピアニストやヴァイオリニスト等を片っ端から聴きまくった。
・マーラーの5番に深い感銘を受けていた。またチャイコフスキーも「あまりの俗っぽさに怒りを覚えることはあるものの」自然さ、みずみずしさが好きだった。
・ロシア5人組に対しては「自然主義、教条的な審美主義(旧態依然のアカデミズム)、ディレッタンティズム(道楽主義を指す。真の美的体験に備えるべき大切な何かを欠いているという否定的な意味)」だ、ということであんまりいいとは思ってなかった。師匠リムスキー・コルサコフも5人組の一人なんだけど、という疑問は浮かぶが、彼の作品は好きだったという記述もあるし、曲によって例外もあったという記述もあるので、あくまで全体の雰囲気としてなのだろう。
リムスキー・コルサコフ師事時代
・リムスキー・コルサコフと会うのは1902年、20歳の頃である。リムスキー・コルサコフは1908年になくなっているので相当晩年の弟子である。音楽院の教授でありながら「音楽院なんて行かなくていいよ」と言われて個人レッスンしてもらってたらしい。彼の葬式においてストラヴィンスキーが献呈した「葬送の歌」という曲があり、「オーケストラ楽器の独奏楽器すべてによる曲で、師の墓に置かれた花輪のように、独奏の旋律を次々を受け渡していく」曲で、本人曰く「火の鳥以前の曲で一番いい曲だった」とのこと。なにそれ聴きたい。だが残念なことに紛失。しっかりしてくれ。と思ったら、なんと2015年に出てきたらしい。
想像よりもずっとしっかりした曲だった。ここにきて紛失楽譜がポロポロ出てくるの面白い。
・20代の頃にプロコフィエフに会った。その感想が「音楽的に思索するタイプではない。音楽的な構造についての適当さに驚愕した。音楽に対しての選択は決まりきっており、間違っていることも少なくなかった」
ちなみにプロコフィエフ側も自伝でストラヴィンスキーに会ったときの感想を記しており、その聡明さに感銘を受け、健気に喜んでいる。
・習作として「スケルツォ(1902)」や「ピアノソナタ嬰ヘ短調(1902-04)」がある。作曲中のこれを見せてリムスキー・コルサコフに師事した。20歳、本人はなくしたとばかり思ってて作品にはカウントされてないが、ストラヴィンスキー没後発掘された。しっかりしてくれ。こちらがスケルツォ。
本人は「ベートーヴェン後期のぎこちない模倣」と言ってたらしいが、ドイツっぽさは感じられない。ストラヴィンスキー的な面倒くささが結構出てて面白い曲だと思う。
・最初期作品のひとつ「牧神と羊飼い(1906)」がナクソスにあった。24歳くらい。
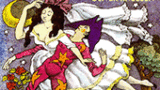
リムスキー・コルサコフはあんまり良いとは思わなかったというが、たしかに安いドビュッシー的な音響の羅列に終止し、光るものもほとんどない。これがストラヴィンスキーかと驚愕するレベルである。ここからリムスキー・コルサコフは猛烈に彼を励まし、次回作を書かせたという。彼の慧眼っぷりは脱帽するほかない。
ディアギレフとの出会い
・「花火」が1909年初演されたところからディアギレフとの交流がはじまる。いうまでもなく後に3大バレエへと繋がる超重要な出来事である。
・ディアギレフは音楽の細かいことはあまりわからなかったがとにかく芸術マニアで、かつ行動力があった。興行家として膨大な改革、企画を成功させた人物で、金があるわけでもないのにダンサーをはじめ各分野の人物を呼び寄せる天才だったという。ちなみにリムスキー・コルサコフに作曲を習ったことがあり、作曲家になりたいと言ったが止められたそうである。リムスキー・コルサコフの慧眼っぷりにはつくづく脱帽するほかないのだ。
・「春の祭典(1913)」構想当時における言及は驚くほど少ないらしい。「人間と大地の結びつき」「簡潔なリズムで到達しようとした」などという書簡のみ。後に「どのシステムにも従わなかった。自分の耳だけが頼りであった」とリムスキー・コルサコフの息子に語っている。
・第一次世界大戦時はスイスへ。オケをやる余裕がなかったので、弦楽四重奏「3つの小品」「コンチェルティーノ」やピアノ曲「3つのやさしい小品」「5つのやさしい小品」など小品が立ち並ぶ。
弦楽四重奏のための3つの小品(1914)
オスティナート、多調性、ポリリズム等がむき出しになる。1910年〜はそういう時代であったという。
その後、音楽哲学について
・1924年あたりから指揮者・ピアニストとして演奏旅行した。自作自演を好んだ理由はとりわけ勝手にテンポを変えられた演奏が嫌いだったからだという。演奏=解釈という姿勢に疑問を持っていた。
・そういった理由から自動ピアノへの興味は非常にあり、1923年に自動ピアノ用に自作を全部作り変えた。1929年にレコード会社と契約しレコーディングにも勤しんだ。「記録として価値を持ち、私の曲の演奏者にとってもよい道案内となるだろう」しかし1935年には「何度も聞いて慣れてしまうと、耳は自然な音響を聴こうとせず堕落してしまう」「でもテンポは守られて、指標にはなるので満足はしてる」みたいなことを言っていた。機器の発明からほんの10年ちょっとで本質をついた発言をしているように思える。
・作曲の順番に対して述べている。
「まず知的好奇心、作ってみたいという欲求がある。そこから手を動かし、なんか出してみる。その後、それに霊感があるような感じがしてきて、曲になっている」とのこと。これはち、あろ「芸術とはすごいもの、俺達がそれを表出させてやるのだ」みたいなドイツ系の芸術神話的な派閥とは真逆である、という意思表示にほかならない。
・「発見と思いつきを混同するな」と述べている。
つまりは「発見」というのは実現可能で、ちゃんと形になるものを言うのであり、「思いつき」はそれを前提としない、一種の刺激だけの状態のもの。「思いつき」を「発見」へ昇華させるには技術がいるし、昇華不可能な思いつきもあるでしょ?ということを言いたいのだろう。
・「偶然を認知することが、霊感を得る唯一の方法だ」と述べている。
このくだりも要するに、「いろんなものを観察してれば、偶然面白いものを見つけたりするでしょ?それを霊感に変えるのよ。まったくなんにもないところに霊感だけ降ってくるなんてことはありえないんですよ」ということであろう。
・「風や鳥の音ってのは音にすぎない。音に秩序を感じられるのは人間のみなわけで、秩序を感じで初めて音楽になる」だから音楽を統べる秩序が大事なわけですね。メロディとして形成する秩序、曲全体の秩序。
・レオナルド・ダ・ヴィンチが言った「芸術は抑圧とともに生まれ、自由とともに死す」を引用している。
つまりは「抑圧されればされるほど自由に作曲できて、一切の抑制がないととたんになにしていいかわからんようになるんだ」と主張している。かなり極端だ。果たしてそうだろうか。
・「伝統と慣習はまったく異なる。伝統は意識され、選りすぐられたもの。慣習は無意識的にそうなったもの。伝統のみが大事でしょう?区別すべし。伝統にあらざるものはすべて剽窃である。」といったことを述べている。
最後が若干話飛んでる感じもなくはないが面白い。
第二次世界大戦前後
・ハリウッドに住んでいたので当然映画音楽の企画もあったが結局どれも実を結ばなかった。ウォルト・ディズニーの「ファンタジア」での「春の祭典」の使用料は驚くべきやすさで、ソ連の人間だったストラヴィンスキーは米国の著作権を取得できなかったのでこれの金も入らなかった。さらに曲の使い方も切り貼りが多く、演奏もだいぶイメージとは異なっていた。
37分くらいから。まぁ確かに原曲とはちがうというか、たぶんにディズニー的というか・・・。
ディズニー側もこれは莫大な費用を書けてて大赤字だったらしいが、とにかく日本人の我々からするとこれが作られたのが戦前というのがつくづくおそろしい話である。
・秩序に関して拘りをもっているストラヴィンスキーだが、第二次世界大戦中に書かれた作品、「三楽章の交響曲」「タンゴ」「エボニーコンチェルト」等には統一性がほとんどない、言い換えれは無秩序に極めて近い、これは、故郷を失い二度目の亡命を行っていたストラヴィンスキーの底知れぬ不安がそうさせているのだ、と著者は語っている。
1950年以降
・1951「放蕩児の遍歴」が世界的成功。69歳。
・金にうるさいストラヴィンスキー。そのエピソードは枚挙にいとまがないが、「トレニ(1958)」の委嘱者の談で「ギャラ1万ドルで委嘱をして、いいよっていうから帰ってきて寝てたら夜中に友人から電話で「たいへんだ、ストラヴィンスキーが寝れないって言ってる。もう千ドル欲しがってるけど言えなかったんだって。」いや千ドルくらい工面するよ、と快諾しにもう一度会うと、ひどく喜んだストラヴィンスキーはお礼にとシャンパンを箱ごと、キャビアを山程注文した。千ドルなんてとっくに吹き飛んだ」という落語のような話がある。トレニというと旧約聖書を用いた合唱曲で初めて12音技法を用いた敬虔でソロの多いいかにもって感じの曲だが、このエピソードと一緒に聴くとちょうどいい具合にオチがついて面白い。まあこのときすでに76歳だから、ボケてるといえばボケてるんだろうけどなあ。。

・1959年来日、武満徹を発見する。
・収入のためにたった一人弟子をとっていた。その弟子の持ってくる交響曲をひたすら修正しつづけるレッスンであった。後年、その弟子だが、あろうことかその交響曲をなくしたらしい。なんたることか。師匠も師匠なら、弟子も弟子である。
・70歳のとき、オランダ国王に祝われた際に「あなたの作品が好きです」と言われた。「で、どの作品が好きなのですか、閣下」と答えたという。どうせ俺の作品なんて知らんやろ、俺の名前だけしか知らんやろ、という皮肉であった。
・ベルクもヴェーベルンも亡くなっていたので、十二音技法に手を出しやすくなったと思い、十二音技法をやった(という側面もあるらしい。)
・ヴェーベルンの「結晶」という考え方が好きだったようで、自作の今までの考え方に、慎重に十二音技法を取り入れていった。「アゴン」「ムーブメンツ」など。「ドデカフォニーで書いた」とは言っていたが、その他の解釈は自分では語らなかった。
・1961年に半世紀ぶりにロシアへ。迎えた人々の様子をショスタコーヴィチが辛辣に観察している。つまりはアメリカに逃げた当時のストラヴィンスキーを国民は罵っていたのに、今更なんやねん、ということを手のひら返して祝福する民衆に対して感じたという。「ストラヴィンスキーもそれを感じでとっとと帰ってった。さもありなん」
・ストラヴィンスキー生涯最後の作品のタイトルは「ふくろうと仔猫ちゃん(1966)」84歳くらい。妻へのプレゼントで、かわいいイラストともに作られたものだという。この5年後になくなるまでは論評やインタビューなど以外は残っていない。

Wikipediaに訳詞も載っている。かわいいんだか不穏なんだかよくわからん曲。
・巻末の各著名人によるストラヴィンスキー論も面白い。サティがだいぶ手放しに褒めてるのも面白いし、ショスタコーヴィチが経過部がなくてわかりやすいから受けたんだろうな的に冷静で辛辣なのも面白い。
ということで
現代にも通ずる問題も多く、読み応えがあった。春の祭典のダンサーにつきっきりでレッスンに取り組んだり、いい人っぷりというか、苦労というか、そういうのもいろいろしていた。世界の事情と自らの理想、人間すべてに深く関わり、いるべき国も含め、その終着点を探し続けた巨人の人生はもっと知られるべきだと感じた。


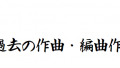

コメント